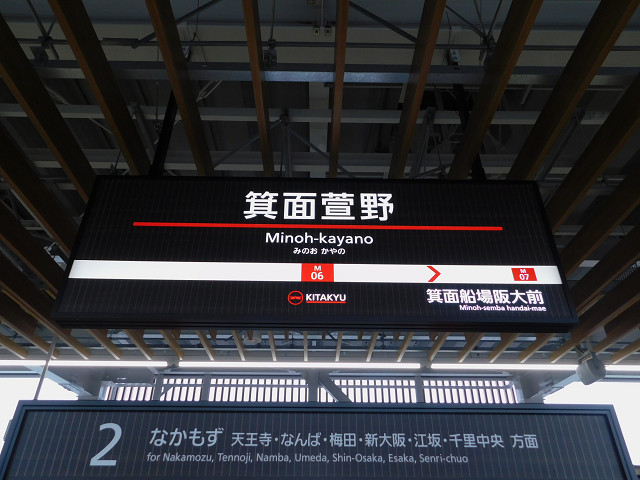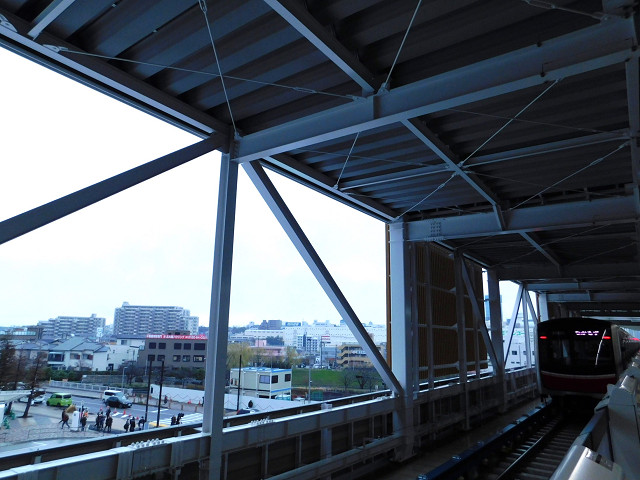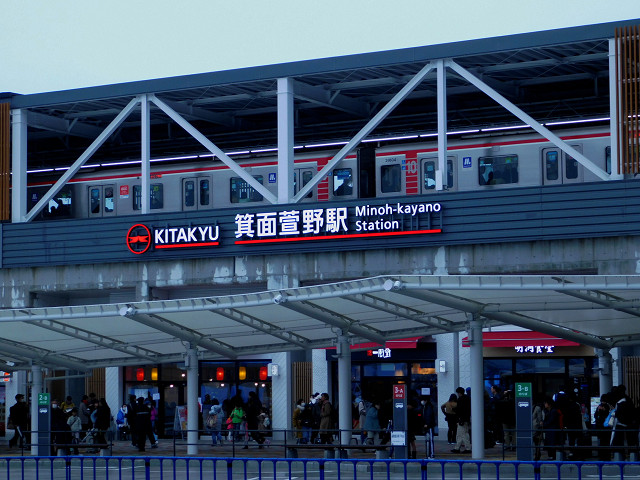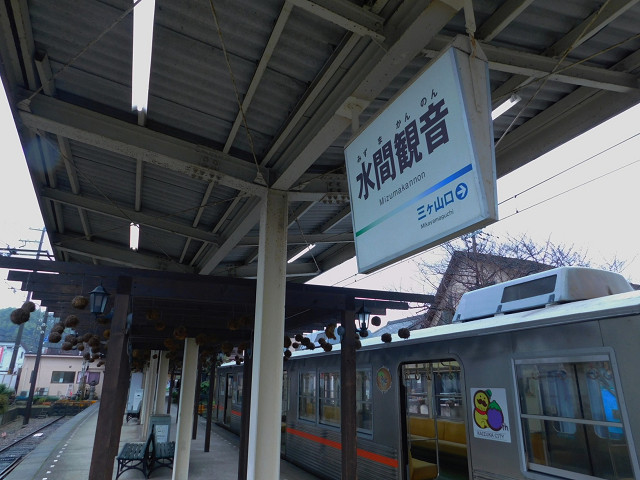前日に無理をしなかったのがよかったようで、3/24は朝早くに起床。当初は朝食後に考えていた行程を前倒しして、出たとこ勝負で乗り降りに臨みました。
ホテルの最寄駅はJRだと新今宮。通天閣口で18きっぷの改札をし、まず向かったのは隣の今宮でした。
今宮は新今宮側から行く場合、大阪環状線でも大和路線でも可。2路線使える駅だからいつでもという訳ではなかったと思いますが、すっかり後回しになっていて、大阪環状線の未乗降駅で最後に残っていたのが当駅でした。大阪環状線のホームが設けられたのが1997年3月の話なので、同線の駅としては最も新しいのだとか。見落としていたというのが正直なところかも知れません。

今宮に着いたのは6:28。次に西九条方面に行くとすると6:36発、49発になるので、ここは8分後ということにして早足での見物としました。大和路線の1・2番線だけを見れば2面2線。その2番線と同一ホームなのが大阪環状線外回りの3番線・・・2階部分は2面3線という形になります。では大阪環状線の内回りはどこにあるのかと言うと、2・3番線の上、つまり3階部分に4番線があるという構造。大阪環状線ホームが後からできた件と関連する訳ですが、これには意表を衝かれました。

その4番線ホームを見に行くには余裕がない感じだったのでひとまず駅の外へ。3階構造の駅にしては西側外観は質素な感じで、これぞ駅舎といった観はなし。存在感という観点では弱めな駅と言えそうです。



ともあれ大阪環状線はこれにて全駅クリア。期せずして、6:36発は「大阪・関西万博」ラッピング列車だったので、そんな記念に相応しい一本になりました。